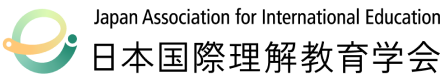会長あいさつ

スリランカ・ペラデニヤ大学にて
第7代会長 永田佳之
日本国際理解教育学会のDNA
去る2022年6月11日に日本国際理解教育学会第31回研究大会に併せて開催された総会にて第7代日本国際理解教育学会会長を拝命いたしました。微力ではございますが、皆さまと共によりよい学会づくりに励んでまいりたいと思っております。3年間、どうか宜しくお願い致します。 会長職に就くにあたり、自問してみたことがあります。それは、日本国際理解教育学会のDNAとは何かという問いです。
たしかに、会員に大学教員のみならず現場の教師が少なくないこと、実践者と研究者が共に研究を進めており、そうした協働が研究会や紀要にも反映されていること、韓国や中国と共同研究を推進していることなどを指摘できるのかもしれません。しかしこれらは他学会でも見られる特徴でもあります。そうこう考えながら学会の歴史をふり返ると、初代会長が天城勲先生であることは殊の外、意味深長なのではないかと思うに至りました。国内の教育改革はもとより、35年以上にわたり関わられたユネスコをはじめ、OECDや日米教育文化会議などで国際的にも活躍した天城先生は、ユネスコの記念碑的な報告書『学習:秘められた宝』の一著者でもあり、元日本ユネスコ国内委員会会長であり、ユネスコ本部職員からも尊敬されていた日本人でした。もちろん文部次官まで務められた官僚という見方もできるでしょうが、本学会にとっての天城先生は国際理解教育の国際的な唱道者であり、世界平和を希求する国際人としてのIsao Amagiなのだと思います。
小生の恩師である千葉杲弘先生(本学会元理事)を通して、天城先生とは直接お話しする機会に幾度か恵まれました。いずれも浅学非才の大学院生時代でしたが、その時の会話は今でも鮮明に覚えています。ある日、小生が国際通の行政官としてどのようにお仕事をされてきたのかという無粋な質問をしたことがあります。その時の答えは「岩壁を登るように、どこにハーケンを打つかを考えながら仕事をしています」でした。おそらく本学会の誕生も打ち込まれたハーケンの1つなのでしょう。
ウクライナやミャンマーの惨状を挙げるまでもなく、国際理解教育をめぐる情勢は待ったなしです。岩壁はより険しくなっているに違いありません。そんな情勢下で、国際理解というミッションを担う私たちはどこにハーケンを打ち進むべきなのか・・・しばらくは正答のない問いを携えながらの舵取りになりそうです。
不確実性の時代の舵取りは困難ではありますが、最後に、この3年間でハーケンを打つべき方向性について私見としてお伝えできればと思います。
本学会には沢山の「宝」がありますが、その1つは現場の教師及び地域の活動家の会員です。そのような会員の皆様が国際的な潮流と出会い、視野を広げ思考を深めていく機会を積極的に提供していきます。また、昨今の厳しさを増す労働環境の中でも地道に実践を重ねておられる会員は少なくありません。そうした会員をはじめ、予測困難な時代を生きる実践者や研究者がエンパワーされるようなネットワークを整えていきます。さらに若手の会員とベテラン会員が活躍する舞台を設け、会員増につなげたいと考えております。
前会長の森茂岳雄先生より受け継いだ課題も優先的に取り組んでまいります。J-Stage(科学技術情報発信・流通総合システム)への登録による会員の皆様の研究成果の迅速な普及、学会規約の整備・改編など、いずれも学会の基盤固めとなる重要課題です。
おりしも本年は国連人間環境会議の開催から半世紀が経つ節目の年であり、皮肉にもその年に勃発したのがウクライナ侵攻でした。激動の国際情勢の中、来年のユネスコ総会に向けて国際理解教育の原点とも言える「国際教育勧告」の見直しも着手されており、国際理解教育の基盤そのものが変容を迫られています。
混迷の度合いを深める時代であるからこそ、いま一度、初志に立ち戻り、現代の文脈の中でその可能性と課題を見極めながら会員の皆様の学びの活性化と深化に寄与していく所存です。そのためにまずもって必要なのは、お一人おひとりの積極的な参加です。どうか学会活動へのご尽力を惜しまれることのないよう、お願い申し上げます。
歴代会長あいさつ文
-
継承と創造̶新たな飛躍に向けて
第6代会長 森茂 岳雄本年6月に椙山女学園大学で行われた第29回研究大会の 総会において、藤原孝章前会長から新たに会長を引き継ぎました。引き続き藤原前会長が提唱された「会員の皆様が元気になる学会」をめざして努力したいと思いますので、会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
新たに会長を引き継ぐに当たり、これまでの会長のもとでの活動や研究の成果を踏まえ、今後3年間の課題を整理し取り組んでいきたいと思います。
(1) 会員の増加と学会財政の健全化
学会が充実した研究活動を行うためには、安定した財源の確保が求められます。近年の日本の人口減少の中で、若い世代の会員の減少が学会の共通の悩みになっています。学会財政を健全なものにするためにも、若い世 代の会員を増やす努力を考え、若い世代に魅力ある活動を展開できるように各委員会を中心に考えていきたいと思います。
(2) 学会創設30周年記念事業の展開
2020年度は、学会が創設されて30年の記念の年を迎えます。学会としては、来年度の玉川大学で開催される第30回記念大会において海外ゲストを招聘して国際シンポジウムを開催する予定です。また30周年記念の出版事業として、これまでの学会による国際理解教育の研究を総括し、今後の課題を提出する出版物の刊行も計画しています。
(3) 研究の充実と会員の研究の公開
学会の第一の任務は、研究の充実と研究成果の公開です。今後も研究・実践委員会を中心に特定課題研究を充実させていくとともに、学会の研究成果を広く公開していきたいと思います。これまで学会誌『国際理解教育』を中心に、他にも書籍の形で会員の研究成果を世に問うてきました。今後さらに研究成果を多くの人に知っていただくために、『国際理解教育』掲載論文のJ-stageへの 公開を検討しています。
(4) 社会連携事業の強化
国際理解教育を推進するにあたって外部機関との連携 の意義は大きいものがあります。本学会もこれまで国立民族学博物館と連携して、国際理解教育の授業づくりや教員研修を行ってきました。国立民族学博物館との連携終了後は、JICA地球ひろばと連携して教員研修を行ってきています。今後は、UNESCO関連機関等との国際連携も踏まえて連携を強化させたいと考えています。
(5) 海外学会等との連携・協力の強化
これまで韓国国際理解教育学会とは、毎年の研究大会への相互の参加、発表を通して交流を重ねてきました。また、日中韓の間では、現在「異己理解・共生授業プロジェクト」を通して実践研究の交流が深められていま す。今後は、これらの交流を継続しながら、新たな3カ国による共同研究の可能性についても探っていきたいと思います。
-
成果の継承と次世代にむけての創造―新たな3年間を迎えて
第5代会長 藤原 孝章去る、7月6、7日の両日にわたって広島経済大学において開催された日本国際理解教育学会第23回研究大会総会 にて、学会の新しい執行体制と今後の 3 年間(2013 〜 2015年度)にわたっての方針が承認されました。
私は、大津和子前会長から新たに会長を引き継ぎました。多田、大津会長時代の6年間(2008 〜 2013年度)は、米田会長時代6年間の会員諸氏の教育実践や研究の成果がまとめられ、出版物の形となって現れました。それは、国立民族学博物館との連携事業の成果物の一つである『学校と博物館でつくる国際理解教育―新しい学びをデザインする』(中牧弘允・森茂岳雄・多田孝志編、明石書店、2009年)であり、科学研究費による共同研究の成果物の一部である『グローバル時代の国際理解教育―実践と理論をつなぐ』(日本国際理解教育学会編、明石書店、2010年)でした。そして、昨年刊行された『現代国際理解教育事典』(日本国際理解教育学会編、明石書店、2012年)は、100名におよぶ執筆者全員が会員であり、学会としての一 つの位置を社会に示し得たものと評価しております。学会誌『国際理解教育』も第16号(2010年)から出版元を明石書店に移し、装丁もあらたになりました。
会員諸氏の研究と実践に支えられた、学会のこのような 活動は、学会の社会的責任でもあり、今後も継承すべきものと考えます。
その意味で、新たな3年間を迎えての学会の課題は、まずもって、これまでの成果の継承です。そのためにも、会員諸氏に資する学会運営が求められます。魅力ある研究大会とそれへの参加、発表、それらをふまえての学会誌の編纂など従来の運営を力強く行っていく必要があります。
次に、21世紀の教育的課題に対応した学会ならではの研究・実践活動の展開が求められます。そのためには、国際理解教育の国際的動向と国内の学校や社会の動向をふまえつつ、しかし時流や時勢を批判的に吟味し、グローバルな学習や地球市民の育成を目標とする基本を見据えていくことが必要です。日韓中共同研究で培ってきたネットワークをより実りあるものにすることも求められています。
以上のような課題に対して、学会運営組織としては、従来の研究と実践の委員会を統合した研究・実践委員会、国 際委員会と紀要編集委員会の3つの委員会と事務局のもとに、新しく出発することにしました。また、理事以外の会 員諸氏を新たに委員として迎えました。標題に「次世代にむけての創造」とした所以です。
新たな3年間は、学会をめぐる内外の状況を適確にとらえ、次世代にむけて新たな課題を創出していくことで、組 織の新陳代謝をはかっていく時代としたいものです。
-
新たな10年に向けて
第4代会長 大津 和子本学会の第20回記念大会が、永田佳之実行委員長のもとに聖心女子大学で盛大に開催され、これまでの実践・研究の成果が披露されました。次の新たな10年を迎える節目に会長を務めることになり、身の引き締まる思いをしています。
さて、過日、国際連合大学の「サスティナビリティと平和研究所」に設けられた「東アジア将来構想フォーラム」に、ゲストスピーカーとして出席してきました。このフォーラムは、「新しい時代の日中韓3カ国を中心にした共同体による地域発展のあり方を考える」ために、文部科学副大臣、国連大学副学長、東アジアの政治および歴史の専門家によって構成された研究会なのですが、そこで「日韓中の協働による相互理解のための国際理解教育カリキュラム・教材の開発」(科研プロジェクト)についての報告が求められたのです。
そこでまず、本学会が「実践と理論をつなぐ」ことを重視しながら実施している各研究プロジェクトや教員研修事業を紹介し、その一つとして、科研プロジェクトの概要について説明しました。そして、具体的な教材として「韓国旅行すごろく」について報告しました。この教材は、日本人児童・生徒が韓国を3泊4日で旅するという設定のもとで、訪れる各地のマスにつくられたクイズに答えたり、「韓国のコマ回し」や「ハングルの解読」といったワークをしながら、韓国の文化や歴史、日本とのつながりを理解していくゲームです。実践の事前と事後のアンケートをもとに、生徒たちの変容について紹介しました。
出席者のみなさまからは、「中国や韓国の学校教員をどうやって研究メンバーに加えることができたのか」「竹島などの政治的問題は含めないのか」などといった質問が出され、活発な議論が展開されました。最終的には、「小中学校の段階では、日本と韓国・中国との論争的な政治問題を取り上げるよりも、むしろ、韓国や中国の文化に興味や関心をもち、マスメディアなどを通じて子どもたちにインプットされた一面的でネガティブなイメージを変えることが重要であることが、大変よくわかった」というコメントをいただきました。また、「科研プロジェクトの成果として開発されるカリキュラム・教材を、ユネスコなどを通じて出版し、3カ国での実践をぜひ進めるように」とのアドバイスも受け、大いに励まされました。
以上は、国際理解教育がまさしく現代日本社会の要請に応える教育であることを示す一例であり、本学会の活動にはますます大きな期待が寄せられています。学校教育においてのみならず、地域においても国際理解教育の実践に取り組んでいくことが、日本の教育の質の向上に貢献することになるとあらためて確信しています。
日本国際理解教育学会のいっそうの発展のために尽力してまいりますので、会員のみなさまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
-
明日の地球社会に 「希望の未来」をもたらす学会へ
第3代会長 多田 孝志7月の総会において会長に推挙され、承認されました。本紙面をかりて会員の皆様にご挨拶を申し上げます。
前会長米田伸次先生は、2期6年間にわたり、高い見識、使命感と情熱をもち、学会の発展に尽力されました。また、今期で理事を勇退された天野正治、新井郁夫、千葉杲弘、中島章夫、樋口信也の諸先生方は、本学会の活動・研究に大きく貢献されました。深く敬意を表すとともに、今後の変わらぬご支援をお願いいたします。
さて、新体制の方針について、総会での提案を基調に、主な内容について、次の2点に集約して記します。
第一に、何よりも、会員のニーズに応える課題についての研究・実践の展開です。
その一は、21世紀の国際理解教育の概念や使命等の考察・解明です。世界の現状を看視しますと、競争と効率が強調される潮流の中で、人間関係、自然との関わりなどが途絶され、個人や少数者の価値観や生き方、尊厳が喪失される傾向が強まりつつあるように見えます。この状況を打破し、共生を基調とした市民社会を構築できる人間を育成する教育としての国際理解教育の意義を再検討し、その使命を明らかにしていくことは、本学会の基本的な課題です。
二つめは、教育現場の実践的課題に応える研究・研修の 推進です。多くの教育関係者たちが、国際理解教育の必要性は認識しつつ、実践の目標設定、カリキュラム開発、学習方法の改善などの具体化に戸惑っている現状がありま す。こうした状況を直視し、教育実践に資する研究・研修 を推進していくことは、本学会の使命と考えます。
会員が学会の諸活動に参加する機会を拡大し、研究・研 修、論議する場を数多く設定することにより、これらの課題を解明していくことができると期待しています。
第二に、知の統合への取り組みです。その一は実践研究 と理論研究との連携です。教育の現場にこそ優れた理論が潜在しています。他方、教育実践は理論的基盤を得てこそ質的向上がもたらされます。両者の統合は、国際理解教育の発展に不可欠です。
二つめは、さまざまな教育資源の活用と地域ネットワークの形成です。関係諸機関、地域の人々などとの連携を組 み込むことにより、視野の拡大、思考の深化、主体的行動力の向上などが効果的に促進されます。このための具体的な方途を探っていくことが必要となります。
三つめは、諸学の研究組織との学際的共同研究、および海外の関連組織との連携の促進です。国際理解教育の概念 や現代的課題の解明には学際的な共同研究や、外からの異なる視点が必要と考えるからです。
会員の皆様の参加、協働、支援を得て、厳しい状況下にある我が国の教育現場と、明日の地球社会に「希望の未来」をもたらす学会にすべく努力して参ります。関係各位のご支援をお願い申し上げます。 -
充実したステップ期の創出を
第2代会長 米田 伸次このたび、はからずも天城勲会長のあとを引き継いで会長をお引き受けすることになりました。日本の教育界の重鎮天城先生のあとだけに、私にとって会長職はとてもにが重く感じられます。学会発足以来11年間、学会を育て、指導下さった天城先生、また天城先生とともに副会長を辞される川端末人、中西晃両先生に、会員を代表して心からの御礼と感謝のことばを申し上げます。
ところで、学会が歩んできたこの11年間は、ポスト冷戦期と重なっており、同時にまた、グローバル化が急速に進展していくという時代でもありました。また、この時期には、周知のように、日本の教育界においても、第15期中教審答申を起点に、21世紀をにらんだ教育の改革が提起され、国際理解教育も今まで以上に強調されるようになってきました。
学会としてもこの11年間、こうした「新局面」に対応した国際理解教育のあり方、進め方について、前向きに取り組み、着実に成果をあげてきたのではないかと受け止めています。しかし、ホップからステップの段階に入りつつある11年目の若い学会が、この「新局面」に対応して、まだまだというより早急に取り組まねばならない積み残した課題も、決して少なくはないように思います。
まずその一は、学会のあり方をもう一度問い直してみるということです。「新局面」に対応した学会の使命や役割とは何なのかという問い直しを中心に据え、学会の存在意義、あり方、方向性を明確にし、そしてそれを全会員が共有していくということです。
その二は、「国際化に対応した教育」として展開されてきた多様な教育の取り組みとの関連で、「新局面」に対応した国際理解教育はどんな役割を荷っていくのか、そのような国際理解教育とはいったい何なのかについても全会員で論議を深めていかねばなりません。
その三は、国際理解教育の研究(者)と実践(者)の連携、相互啓発をどう進めていくのかということです。学会は、発足当初から、研究者だけでなく、学校・社会教育関係者、さらにはNGO・NPO関係者等も含めた幅広い層を包含した新しい学会づくりをめざしてきました。しかし、連携や相互啓発はことばとして語られてはきましたが、深まりを見せてこなかったように思います。果たして国際理解教育に研究と実践の明確な線引きが存在するのかという問いかけも含めて、連携、相互啓発を深めつつ、国際理解教育研究の水準をいかに高めていくのかという論議と実践を全会員で進めていかねばなりません。
無論、学会の抱える課題は決してこれに尽きるものではありません。大切なことは、会員が積極的に問題を提起し、論議に参加していく場、機会がどれだけ確保されるのかということ、そして全会員がこれらの課題を共有し、解決に向けて話し合っていくことではないかと思います。このことこそが会員を拡大し学会を発展させていく基本的な条件ではないでしょうか。
幸い、多田孝志副会長という強力なパートナーを得、また意欲いっぱいの理事によって理事会が構成されているということは、学会のこれからに明るい希望を抱かせてくれています。
学会に、実りのあるステップ期を創出していくよう、会員の皆様にも一層積極的なご参加をどうかよろしくお願い申し上げます。
-
国際理解教育の視点
初代会長 天城 勲国際理解教育についての考え方は、時期により、国により、立場によりさらに視点により必ずしも一義的ではない。従って実践的な活動や研究の面からみるときわめて多様である。しばしば国際理解教育には包括的な理論構成が弱いという批判が向けられる。ここでは包括的な理論構成の前段階として、現に国際理解教育ちおう諸分野を私なりに大雑把に鳥瞰してみたい。
(1) 国際理解教育について最も包括的な捉え方の例はユネスコの1974年の勧告に見ることが出来る。この勧告の表題そのものが「国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告」と長い名前になっている。当時この勧告原案作成の政府間会議に出席していた私自身最初は大変驚いたのであるが、これにはそれまでのユネスコにおける国際理解の重点の変遷、各国の置かれた立場の違い、特定の理念の強調さらに当時の国際事情等を巾広く含めなければ成立しえなかった事情がある。従って国際理解教育についてはきわめて包括的な観点に立っている反面、理論構成については必ずしも筋が通っていないうらみがある。いづれにしてもこの勧告を軸にユネスコの創立以来の国際理解教育に関する動向は十分検討に値する。
(2) 異文化間の理解。異なる文化−人々の生活様式、思考様式、具体的には生活と風習−を知らないことが人々の間に疑惑と不信を起こし、この疑惑と不信のために諸国民の不一致が余りにもしばしば戦争の原因となったという歴史的な反省と認識から、ユネスコの国際理解教育には異文化間の相互理解の観点が強調されている。わが国においても、経済の世界的規模への発展に伴い日本異質論や日本文化特殊論が引きおこされている。経済、技術、企業など一見文化と関係のない分野のビヘイビアに深く結びついた日本文化のあり方に関心が集り、進んで日本人、日本文化が改めて問い直されている。異文化との交流、受容、共存等の本質論をふまえての教育論議で、例えば在外日本人子弟教育、帰国子女教育の課題もこの系譜に属するし、地方で活性化している草の根レベルの国際交流活動も交流を通じての異文化相互理解であろう。
(3) 普遍的理念の教育。ユネスコでいち早く取り上げた世界人権宣言に基づく人権教育がその代表であり、1974年勧告の表題にも示されているようにユネスコの国際理解教育を貫く一つの普遍的理念である。この系譜としては人権、自由、平和の教育が普遍的理念として繰り返し取り上げられているが、一面では人権と部族、民族の関係や平和即反戦の具体的な活動との関係で理念の政治家が現実には問題となっている。
(4) 他国の理解。ある国から見て歴史的、文化的、政治的或いは経済的にとくに利害関係の緊密な特定国を対象とする国際理解教育の分野がある。わが国のひち日米理解教育はその例であり、さらには韓国、中国に対しては過去の歴史上の特殊な関係に基づく国際理解教育、またわが国の経済上の緊密化に伴う東南アジア諸国に対する理解教育などが大きくはこの類型に入るであろう。
(5) 開発のための教育。世界の三分の二の開発途上国の教育をいかにして整備し充実し発展させるかという開発と援助に係わる教育課題で、現実には無視出来ない重要な視点であり課題である。とくに開発教育とも言われるが広い観点では国際理解教育に含められている。近年この文脈で識字教育、婦人教育、人口教育等の課題が取り上げられているが、これは前述の人権教育の理念にも連なっている。
紙数の関係でその他省いた分野も多い。国際理解教育は学際的であり、かつ知識、技術、価値、態度に係わる実践的教育活動である。しかし、具体的場面ではかなり部分的アプローチとなる。それだからこそ国際理解教育の指導理念の確立とその理論構成は、個別実践活動の位置づけとそれを支えるためには進めなければならない重要な課題である。
学会諸規程
規約
第1条(名称) 本会は、日本国際理解教育学会 (Japan Association for International Education) と称する。
第2条(目的) 本会は、国際理解教育の研究と教育実践にたずさわる者が、研究と実践を通じて、国際理解教育を推進し、その発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年次大会の開催、その他の研究会の開催
(2)会報、紀要等の出版物の編集・刊行
(3)研究調査活動の実施と促進
(4)海外の研究者・教育実践者との交流
(5)その他、本会の目的を達成するに適当と思われる諸活動
第4条(会員) 会員は、正会員、学生会員、団体会員とする。
2. 正会員は、本会の目的に賛同する者とする。正会員になろうとする者は、正会員 1 名の推薦を受けて、事務局に届け、理事会の承認を得るものとする。
3. 学生会員は、本会の目的に賛同し、学生の身分を有する者とする。学生会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を受けて、事務局に届け、理事会の承認を得るものとする。
4. 団体会員は、本会の目的に賛同する団体とする。団体会員になろうとする団体は、正会員1名の推薦を受けて、代表者が事務局に届け、理事会の承認を得るものとする。団体会員は、議決事項を除き、本会の事業に参加できる。
5. 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
6. 会員は、会費の納入を怠った場合、会員としての資格を失うことがある。
第5条(会費) 入会金及び会費の金額は理事会が提案し、総会において決定する。
2. 正会員の会費は、年額8,000円とする。
3. 学生会員の会費は、年額4,000円とする。
4. 団体会員の会費は、年額30,000円とする。
5. 入会金は、3,000 円とする。
第6条(役員) 本会の事業を運営するために次の役員を置く。役員は正会員が担うこととする。
会長 1名
副会長 1名又は2名
事務局長 1 名
理事(常任理事を含む) 若干名
監事 2名
2. 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長が事情によってその職務を遂行できない場合は、それを代行する。
4. 事務局長は、常任理事を兼務し、本会の事務を所掌する。
5. 理事は、選挙によって選出される者(選挙選出理事)と本会の研究活動の推進及び専門領域等の均衡を図るために会長の推薦によって選出される者(会長推薦理事)からなり、理事会を組織し、本会の事業を企画・執行する。
6. 常任理事は、常任理事会を組織し、本会に設置される委員会及び各種事業を企画・執行する。
7. 監事は、本会の会計を監査する。
第7条(役員の選任) 選挙選出理事は、会員の投票により正会員から選出される。選出方法は、理事会において別途定める。
2. 会長推薦理事は、会長が正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。但し、会長推薦理事の数は選挙選出理事の半数を越えることはできない。
3. 会長及び副会長は、選挙選出理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
4. 常任理事は、選挙選出理事の互選により相当数を選出し、総会の承認を得る。
5. 事務局長及び監事は、会長が提案し、総会の承認を得る。
第8条(役員の任期) 役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。任期が開始する年度の4月1日時点において満70歳以上の者は役員となることができない。
第9条(顧問) 本会には顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
3. 顧問は、本会の事業に関する会長の諮問に応じ、また、必要に応じ本会の事業に関し、会長に意見を具申することができる。
第10条(総会・理事会・常任理事会) 本会に総会、 理事会及び常任理事会を置く。
2. 総会は、正会員、学生会員をもって組織し、本会の最高の議決機関として、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議し決定する。総会は定例総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回の年次研究大会のときに開催する。臨時大会は会長が必要と認める場合、随時開催する。総会での議決は原則として出席者の過半数をもって行う。
3. 理事会は、会長及び理事をもって組織し、総会に提出する本会の事業並びに予算・決算に関する議案を審議する。
4. 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって開催することができる。
5. 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって組織し、理事会の委嘱を受けて本会の業務を執行する。
6. 理事会、常任理事会には必要に応じ、構成員以外の者の出席を認めることができる。
第11条(委員会・各種事業) 本会には、各委員会、 各種事業担当部署を置く。
2. 本会に常置する委員会は、紀要編集委員会、研究・実践委員会、国際委員会、広報委員会とする。
3. 各委員会の業務は、理事会において定めるものとする。
4. 会長の発議により、本会に特別委員会を置くことができる。特別委員会の設置期間及び業務は、理事会において定めるものとする。
5. 各委員会は、理事によって組織し、当該委員会の業務を執行する。
6. 各委員会の長は常任理事とし、会長が委嘱する。
7. 各委員会の副委員長は委員長の委嘱もしくは委員の互選とする。
8. 各委員会に協力委員を若干名置くことができる。協力委員は本学会員とし、理事会の承認をもって委嘱する。
9. 各種事業は、常任理事会が管掌し、必要に応じて担当理事及び協力委員を若干名置くことができる。
第12条(所在地・事務局) 本会の事務局を名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 曽我幸代研究室に置く。
2. 事務局には事務局長に加えて、職員を若干名置くことができる。
3. 事務局に職員を置く場合は、正会員の中から事務局長が推薦し、理事会及び総会の承認を得る。
第13条(会計)本会の経費は会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条(規約の改正)本規約は、理事会の承認を得て、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。
付則1 この規約は 1990(平成 2)年1月26日の日本国際理解教育学会の設立総会において制定し、その日より発効する。
付則2 この規約は 1995(平成 7)年1月22日から施行する。
付則3 この規約は 1998(平成 10)年6月14日から施行する。
付則4 この規約は 2001(平成 13)年4月1日から施行する。
付則5 この規約は 2001(平成 13)年6月9日から施行する。
付則6 この規約は 2004(平成 16)年6月6日から施行する。
付則7 この規約は 2007(平成 19)年7月28日から施行する。
付則8 この規約は 2010(平成 22)年7月3日から施行する。
付則9 この規約は 2011(平成 23)年4月1日から施行する。
付則10(委員会・各種事業に関する条項の追加等に伴う一部改正)この規約は 2016(平成 28)年4月1日から施行する。
付則11(事務局所在地の変更に伴う一部改正)この規約は 2017(平成 29)年4月1日から施行する。
付則12(条文の精緻化等に伴う一部改正)この規約は 2019(令和元)年6月15日から施行し、2019年4月1日から適 用する。
付則13(事務局移転に伴う一部改正) この規約は2022(令和4)年6月11日から施行する。
倫理綱領
日本国際理解教育学会は、多様な文化や社会事象を対象とする広領域かつ横断的で総合的な研究を推進して社会に貢献することが期待されている。したがって、本学会の会員(以下、会員)は、この期待に応えて、基本的人権 を尊重し、学会としての社会的責任を履行して、会員による研究の妥当性と公正性を高めることが求められている。これらの実施に当たって、以下の倫理綱領を制定する。
本綱領は、会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員には自覚と責任をもって国際理解教育の下、研究・教育・実践活動において、その対象者の健全な成長と教育研究の発展に寄与することが求められる。
本学会は、上記の主旨に基づき、以下の条項を定める。
1. 基本的人権の尊重
会員はすべての人間の基本的人権と尊厳を尊重し、研究の対象者、及び活動に関わるすべての組織・集団と個人の権利を侵害しないよう努力しなければならない。
2.研究の実施に伴う責任
会員は、研究の実施にあたって、国際理解教育の発展に寄与しようとする積極的意思をもたなければならない。研究の対象に対して常に敬意を払い、並びに事実の公平・公正な解釈と事実に基づく証明に努めなければならない。 研究成果を捏造してはならない。
3.成果の公表に伴う責任
会員は、研究成果の公表に際しては、以下の点に留意し、研究者としての社会的責任を自覚して行わなければならない。
(1)調査協力者には事前に承認を得て、本人の了解なしに個人が特定されることがないようにする等、個人のプライバシー、及び社会的規範を侵す行為をしてはならない。
(2)研究成果の剽窃・盗用、データの改ざん・捏造等、著作権を侵害するような行為をしてはならない。
(3)二重投稿(他学会紀要等に、同一時期に内容・記述が大幅に重複する研究論文を投稿)してはならない。
(4)共同研究の場合には、共同研究者の同意を得るとともに、その権利と責任に十分配慮しなければならない。
4.情報提供者・研究協力者への説明責任・人権尊重
会員は、研究のための情報提供者・研究協力者について、研究の目的、方法およびその成果の公表に関して説明責任を負うとともに、情報提供者・研究協力者の人権を尊重し、個人情報などの秘密保持に配慮し、名誉を傷つけることおよび身体的苦痛や心理的苦痛を与えることがあってはならない。
5.秘密保持・情報管理
会員は、教育・研究等の活動にともなって得られた情報を厳重かつ適正に管理し、研究等に関わる社会的規範の範囲をこえて、こうした情報等を目的以外に使用してはならない。併せて、プライバシーに関わる情報については、関連する法規範を遵守しなければならない。
2018年6月16日総会にて承認

設立について
設立
日本国際理解教育学会は、1991(平成3)年1月26日に東京都港区の「はあといん乃木坂健保会館」において設立総会を開き誕生しました。設立発起人は天城勲現会長他41名の各界の方々で、会員数290名でした。
設立の趣旨
設立総会で配布された設立の趣旨は次のようになっています。
「21世紀を目前に控え、東西対立の冷戦構造が緩んで世界は新しい秩序をもとめて模索をはじめた。物、金、情報そして人間が国境を越えて活発に交流し合い、各国、国民の相互依存関係がますます強まってきた。
反面、民族、伝統、文化、言語等の違いによる競争、対立、誤解、摩擦も日常化し、国民相互の理解交流の大切さを示している。さらに環境問題など地球規模の新しい課題が我々の視野を全人類と来たるべき世紀に向けさせている。
人々の心に平和の砦を築くという精神の下に、ユネスコが永年唱えてきた平和と異文化理解を軸とする国際教育の必要性が今日ほど高まったときはない。国際教育は知識、技術、思考力、価値観、態度形成にわたる教育実践である。
生涯教育の場で、学校、家庭、地域、社会のあらゆる機会を利用し、関係者の連携と協力の体制を整える必要がある。
東洋の太平洋に浮かぶ我が国が、21世紀に向けて、東洋と西洋を結び、南と北を繋ぎながら、世界の諸国民と平和共存するためには、人々の心に国際教育の重要性を訴えなければならない。
我々はここに、研究者、教育実践者、その他の関係者を糾合して、日本国際理解教育学会を発足させ、国際教育の研究と実践、諸国民との交流を通じて、我が国の国際教育の促進、発展に寄与することを決意した。

組織
2022年度~2024年度 日本国際理解教育学会 役員・事務局・各委員会・事業分担一覧
所属は2022年4月1日現在
役員 (五十音順)
| 会長 |
永田佳之聖心女子大学 |
|---|---|
| 副会長 |
釜田聡上越教育大学 中山京子帝京大学 |
| 常任理事 |
石森広美北海道教育大学 桐谷正信埼玉大学 小林亮玉川大学 曽我幸代名古屋市立大学 |
| 理事 |
伊井直比呂大阪公立大学 市瀬智紀宮城教育大学 菊地かおり筑波大学 橋崎頼子奈良教育大学 原瑞穂上越教育大学 福山文子専修大学 藤原孝章同志社女子大学 松倉紗野香埼玉県立伊奈学園中学校 嶺井明子前筑波大学 森田真樹立命館大学 山西優二早稲田大学 |
| 監事 |
林敏博名古屋市立大学 天野幸輔名古屋学院大学 |
事務局
| 事務局長 |
曽我幸代 |
|---|---|
| 事務局次長 |
孫美幸文教大学 和田俊彦跡見学園中学校高等学校 |
委員会・各種事業
| 研究・実践委員会 |
石森広美委員長 市瀬智紀副委員長 橋崎頼子 吉村雅仁奈良教育大学 由井一成早稲田大学 風巻浩東京都立大学 南雲勇多東日本国際大学 |
|---|---|
| 紀要編集委員会 |
桐谷正信委員長 森田真樹副委員長 川口広美広島大学 渋谷真樹日本赤十字看護大学 坪田益美東北学院大学 松尾知明法政大学 松倉紗野香 |
| 国際委員会 |
小林亮委員長 嶺井明子副委員長 原瑞穂 上別府隆男福山市立大学 タスタンベコワ・クアニシ筑波大学 阿部裕子東京福祉大学 |
| 広報委員会 |
中山京子委員長 福山文子副委員長 菊地かおり 神田和可子聖心女子大学 |
| 社会連携事業 |
藤原孝章委員長 岩坂泰子広島大学 |
| 異己プロジェクト事業 |
釜田聡委員長 姜英敏中国・北京師範大学 |
| 重点課題事業 |
山西優二委員長 伊井直比呂副委員長 横田和子広島修道大学 |
| 海外学会等連携 |
金仙美韓国・中央大学校 姜英敏 |