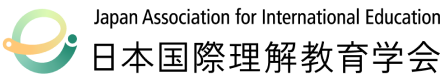プロジェクト情報
現在、本学会では特定課題研究と「異己」プロジェクトの2つのプロジェクトを実施しています。
特定課題研究
2022-2024年度の特定課題研究は、1.外国語教育と国際理解教育、2.教員養成と国際理解教育、3.地域の多文化化と国際理解教育という相互につながる3つのプロジェクトで構成されています。1は小・中・高の10 年間の英語教育をどのように接続・連携し、発展させていくのかが課題です。2は外国語教育、地域の多文化化を担う教員をいかに養成するか、3は学校、地域、NPO、社会などのさまざまな場を通して多文化化する地域の教育を問うものです。
「異己」プロジェクト
「異己」プロジェクト(日中韓「異己」理解・共生授業プロジェクト)は、本学会の国際委員会の活動を契機として、2014年から日中韓の研究者・実践者で始まりました。
「異己」とは、価値多元社会において異なる価値観や立場を持つ相手を意味し、個人間から国家間のコンフリクトを解決する概念です。
理論検討から始まり、授業実践を日中韓で重ねることで、「異己」との共生について考えるきっかけをつくってきました。
引き続き、価値観の異なる集団間の対話形成プロセスをつくり、「異己」理解と共生へのアプローチについて問うていきます。
その他の活動
国際委員会による国際協働事業
「北東アジア平和教育共通カリキュラム開発プロジェクト」
本学会は、APCEIU主催「北東アジア平和教育共通カリキュラム開発プロジェクト (APCEIU’s cooperative project, ‘Development of a Common Curriculum for Peace Education in Northeast Asia’2022-2023)にパートナー団体の1つとして参加しています。 これは、APCEIU (The Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding アジア太平洋国際理解教育センター)が日中韓のパートナー団体(ユネスコ北京事務所・南京大学ユネスコチェア・九州大学ユネスコチェア・日本平和学会平和教育分科会・日本国際理解教育学会・韓国国際理解教育学会)に呼びかけ、ユネスコが提唱する平和の文化のための教育に関する北東アジア(主に日中韓)共通のカリキュラム開発を進め、この地域の平和教育の発展に貢献することを目的としたプロジェクトです。2022年5月からパートナー団体とのオンライン協議がはじまっており、2022年8月には第1回ワークショップが韓国ソウルにて開催され、共通カリキュラムガイドについての話し合いが行われました。http://www.unescoapceiu.org/post/4549?&page=4
2023年3月には第2回ワークショップが福岡市で開催される予定です。最終的には「北東アジア平和教育共通カリキュラムガイド」を出版することを目指しています。
本学会では、本プロジェクトへご協力いただける方を広く募集しています。「ユネスコの平和の文化のための教育」に興味がある方、日中韓共通カリキュラム開発に関心がある方、本プロジェクトに関心がある現職教員の方、ぜひ以下のリンクからご登録ください。本プロジェクトに関する情報やオンライン会議、第2回ワークショップなどについてお知らせさせていただきます。
https://forms.gle/FmvKpf1U2RQm4eSP7
多くの皆様のご登録をお待ちしております。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
日本国際理解教育学会 国際委員会
jaie_international_2022@googlegroups.com
社会連携事業
社会連携事業はすでに10年以上の長い歴史があります。
2018年までは、国立民族学博物館との博学連携共同プロジェクト「博学連携教員研修ワークショップ」が中心で、その成果は出版物として『学校と博物館でつくる国際理解教育-新しい学びをデザインする-』(中牧弘允・森茂岳雄・多田孝志編、2009年、明石書店)などにまとめられています。
国立民族学博物館との連携事業の終了後、現在取り組んでいるのが、JICA地球ひろばの「国際理解教育/開発教育指導者研修」プロジェクトです。学会は2018年以後プロジェクトの後援団体として、教員研修の具体的な内容、方法、授業実践のアドバイスとコーチングに参画しています。成果物としては『実勢事例集』(2020年度、2021年度版)がJICA地球ひろばから刊行されています。
もう一つは、韓国国際理解教育学会やアジア太平洋国際理解教育センター(APCEIU)との連携事業です。昨年から続いている共通の絵本を教材として使った日韓中の「ストーリーテリング」プロジェクトと日韓教員交流のプロジェクトです。国際理解教育(世界市民教育・グローバルシティズンシップ教育)を通じた授業実践、教員研修を目的としたものです。
詳細は、学会誌『国際理解教育』Vol.27,28をご覧ください。また、学会の公式facebookにおいても、プロジェクトの開催や応募情報、活動報告を随時していますので、ご参照ください。
重点課題
重点課題事業タスクでは、以下のような目的のもと、活動を実施しています。
1.重点課題事業の目的
世界的に国家的な価値が強調され、また国家間での対立・緊張が高まる中で、教育の場でも、既存の価値や体制への順応化が進んでいるもしくは進んでいくことが危惧されます。このような中で、教育を通して平和の実現をめざす当学会として、このような動きへの対抗軸、オルタナティブとなるメッセージを共有し、実践者・研究者が平和に向けて相互にエンパワーメントし合う関係づくりにつながる事業をつくり出すことを、重点課題事業の目的としています。
2.重点課題事業の活動
現在は、大きくは以下の3点の活動を企画・実施しています。
① 記念誌『国際理解教育を再想像する:日本のユネスコ加盟70周年記念関連事業報告書』(Web報告書・冊子報告書)の作成
② 「平和の文化」をテーマとする連続トークの実施
③ 2023年度のユネスコスクール(ASP)の70周年に向けた事業の実施

次のイベント